梅雨もまだ明けず、じめじめとした気温が続きます。そんな時期に、辛い行為かもしれませんが、「正座」についてお伝えします。
正座の歴史は意外に新しく、本格的に普及したのは江戸時代中期以降です。しかし、戦後に住宅の洋風化が進み。畳の部屋が減少し、現代に至る過程で正座の機会が激減しました。今では寺院でも、葬祭会館でも椅子が基本です。
「正座」、実は私も得意ではありません。座っていられる「慣れ」は身についたものの、すぐに立ち上がることはどうしてもできない。。。お恥ずかしい限りです。
修行中は正座のしすぎで膝やふくらはぎがあざで真っ黒になった経験もあります。しかし、正座の方が腰の痛みや疲れは少なく、またお腹に力が入りやすくなるためお念仏の発声には適しています。まさに、一長一短です。そして、「正座」に込められた意味は相手への敬意の表現 自己の謙虚さの表明です。
医学的にも、適度な正座は姿勢改善や精神集中に効果があることも分かってきました。
お仏壇の前、大切な方の前、大事なお食事の時、わずかな時間で構いません、「正座」を試してみてください。悪いことばかりではないはずです。でも、くれぐれも無理をして、すぐに立ち上がったりしないようにお気をつけください。転びます。
南無阿弥陀仏
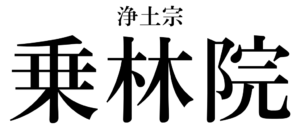
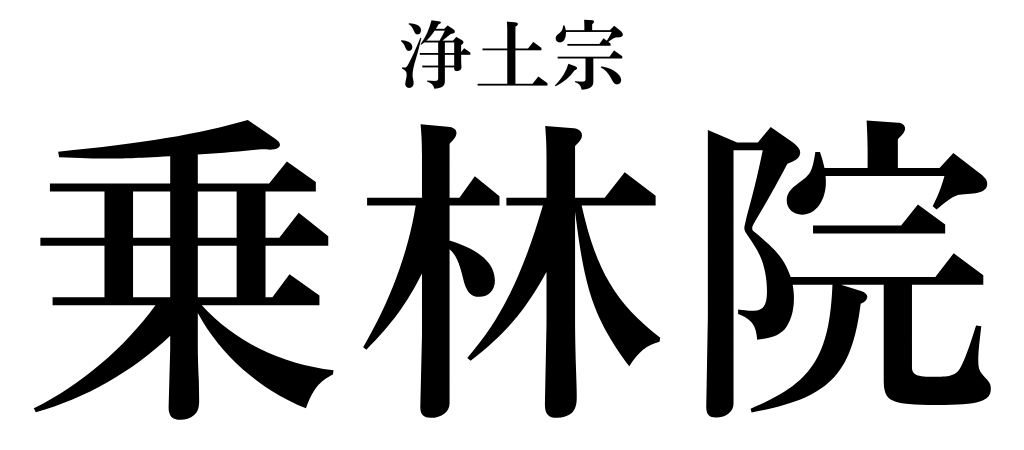
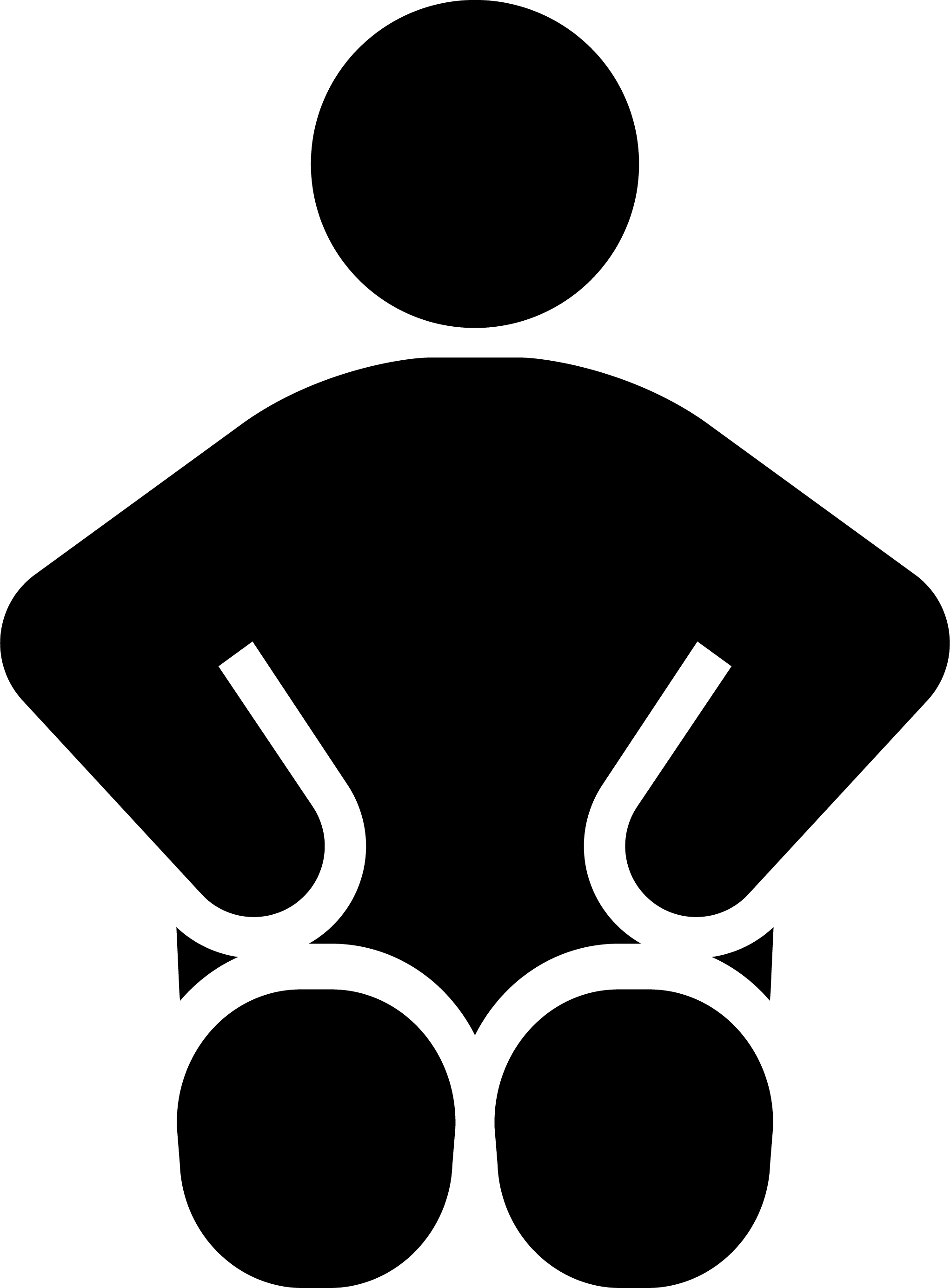
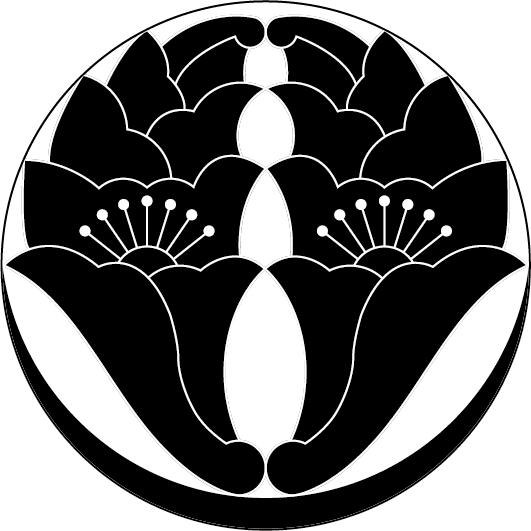








コメント